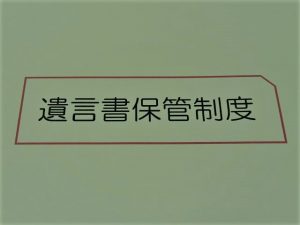こんにちは。司法書士の片岡和子です。
昨年から持ち越してる仕事はいろいろとあるのだけど・・・
昨日書いた遺言書保管制度について、さらに書いておきたいことがあり、まずはこちらを片付けることに。
昨日は、「検認は不要になるけれど、戸籍集めが不要になるワケではない」というお話でした。
遺言を作成しておこうかな、という方には「遺言の内容がどんなプロセスを経て実現されて行くのか」のイメージを持っていただきたいなあ、と思います。
そうすれば、公正証書遺言にするのか、自筆証書遺言にするのか、遺言書保管制度を利用するかどうか、見えてくると思うのです。
昨日のお話が一助になればいいなあ、と思ってます。
で、今日は「遺言の内容」について。
「遺言書を保管する法務局では、遺言の内容をチェックしてくれるワケじゃない!!」というお話です。
この点、誤解・思い違い・カン違いが多発しそうで、ちょっと心配してるのです。
遺言書保管制度は、遺言書「保管」制度です。
「保管してくれる」のが目玉なのです。
改ざん、偽造といった心配がない、というところがキモなのです。
自分で作成した遺言書を法務局に持ち込んで保管してもらうのですが、保管申請の際には厳格な本人確認が行われます。
保管された遺言書は、遺言者が亡くなるまでの間は、遺言者以外の者が見ることも手を出すこともできません。
「遺言書を預かっていた兄が改ざんしたに違いない!!」といった騒ぎが起きない、ということなのです。
保管してもらう遺言書の形式もきちんと決まっています。
用紙はA4であるとか、余白も決められているとか。
保管の申請書も、必要事項をきちんと記載しなくちゃなりません。
遺言書保管の事務処理は「きちんと」行われます。
実はこの「きちんと感」が曲者なのですねえ。
「これで安心、これで大丈夫!!」という気分になってしまうと思うのです。
でも、法務局では内容のチェックをしてくれるワケではありません!!
持ち込まれた遺言書の形式面がOKなら、それをそのまま厳格に保管する、それだけなのです!!
たとえば、次のような遺言書が持ち込まれたとしましょう。
遺言書
自宅は長男一郎に相続させる。
マンションは二男二郎に相続させる。
令和3年1月5日
甲野太郎 印
形式的にOKであれば、これがそのまま保管されます。
甲野太郎さんが亡くなった後、長男の一郎さんは遺言書情報証明書の交付を受けて、自宅の名義変更をしようとするのですが・・・
「『自宅』じゃわかりませんよ」と言われて、名義変更の申請を受け付けてもらえない・・・なんてことが起きてしまうのです。
本人や周囲の人には「自宅」が「○○市□□町にある一戸建て」であることがアタリマエでも、申請を受け付ける側からすると、「一体どの不動産のこと? 所在や地番、家屋番号などで特定してもらわないと。」ということになってしまうのです。
話は戻って、遺言書保管の申請の場面。
申請を受け付けた法務局の職員が遺言書を見て、「これじゃダメですよ、これでは将来名義変更には使えないですよ。」と言ってくれるかというと、そうじゃない、ってことなのです。
気がついたら指摘してくれてもいいじゃないか、と思うかもしれませんが、それはできません。
あくまでも遺言書「保管」制度ですから。
「内容」は、この制度の枠外なのです。
ですから、この制度を利用する際には、「持ち込む遺言書は自力で完璧に作成する」ことが必須なのです。
自分で勉強する、専門家に相談する等して、内容がきちんと実現されるような遺言書を作成することが必要です。
この点に自信がない場合には、公正証書遺言の作成を考えた方がよいのかな、と思います。
☆こちらの記事も読んでみてね☆
★【遺言書保管制度】①検認は不要だけど「戸籍集め」はやっぱり必要。
★【遺言書保管制度】③公正証書遺言と比較・結局費用の問題なのかな。